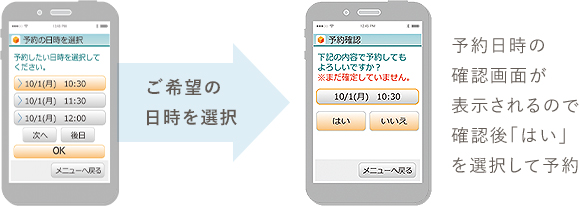Polypectomy 大腸ポリープ切除(日帰り手術)
治療内容についてTreatment Details
検査で発見したポリープを、同日そのまま切除が可能
大腸ポリープを認めた場合、検査同日に切除します。
生理食塩水を局注後にスネアとよばれる器具を用いてポリープを切除します。
切除したポリープはすべて回収し、病理検査に提出します。担かんしている場合もありますので、病理結果を確認し、追加治療の必要性を判断します。
ポリープ切除を可能とする条件
- ポリープ条件内視鏡観察で切除可能と判断されるポリープ
※サイズや形態から一括切除が困難と判断される場合、切除困難な場所にある場合などは、切除できない場合があります。
- 受診者条件 出血傾向の認められない受診者
切除後1週間以内に飲酒、スポーツ、温泉入浴、旅行、出張などの予定がない受診者
- その他
担当術者の判断で安全な切除が不可能と判断された場合は行いません。

Step01ポリープを確認

Step02ポリープ近傍の粘膜下層
に生理食塩水を局注
に生理食塩水を局注

Step03スネア(鉄の輪)を腫瘍の
遺残がないように引っ掛ける
遺残がないように引っ掛ける

Step04スネアを絞って通電する

Step05ポリープを切除し、
病変を回収する
病変を回収する

大腸ポリープ治療後の
注意事項
 食事
食事
1週間は控える
香辛料が多い物、脂っこい物、アルコール飲料・炭酸飲料、カフェイン飲料・生もの など
 運動
運動
1週間は控える
ゴルフ・テニス・ジョギングなどの腹圧のかかる運動、旅行・出張もお控えください。
 風呂
風呂
3日間は控える
長風呂は3日間は避け、シャワー程度にしてください。
 トイレ
トイレ
出血について
お通じに少量の血が混ざることがあります。量が多い場合、長引く際は至急ご連絡ください。
- 1週間は刺激の強い食べ物(香辛料が多い食べ物、脂っこい食べ物など)や飲み物(アルコール飲料、カフェインがはいった飲み物、炭酸飲料など)生ものの摂取は控えて下さい。
- 散歩などの軽い運動は翌日から可能ですが、腹圧のかかる運動(ゴルフ・テニス・ジョギングなど)は1週間控えてください。1週間は旅行や出張は控えてください。
- 3日間は長風呂を避け、シャワー程度にしてください。
- お通じに血液が混ざることがあります。少量の出血なら心配いりませんが、出血が持続する場合や出血量が多い場合は至急連絡してください。
費用・ご予約についてCost and Reservation
費用について
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| ポリープ切除手術・ 組織検査あり | 約9,300円〜 12,800円 | 約18,600円〜 25,000円 | 約29,000円〜 39,000円 |